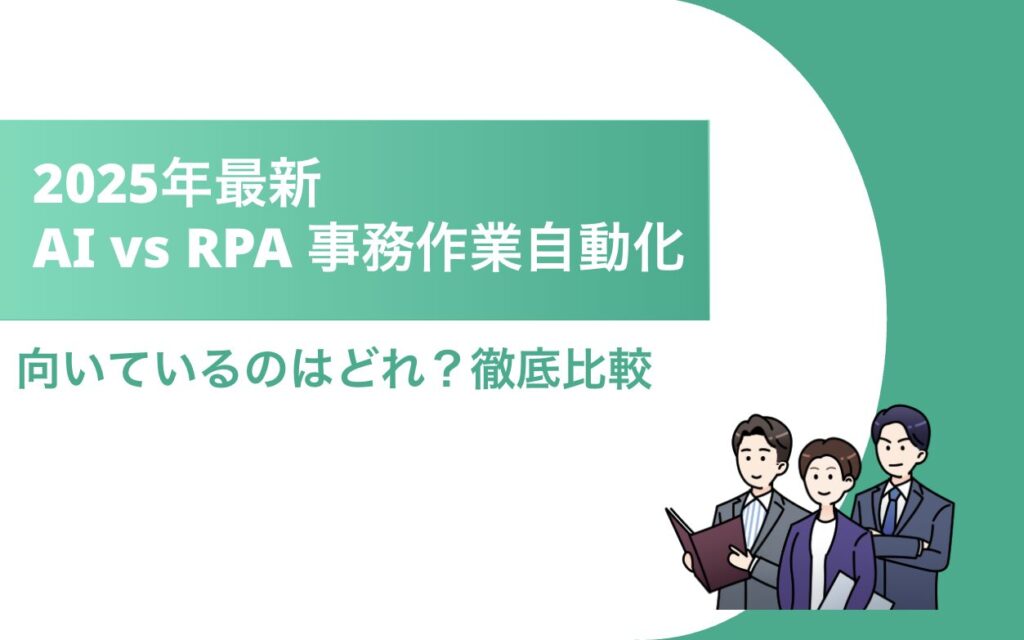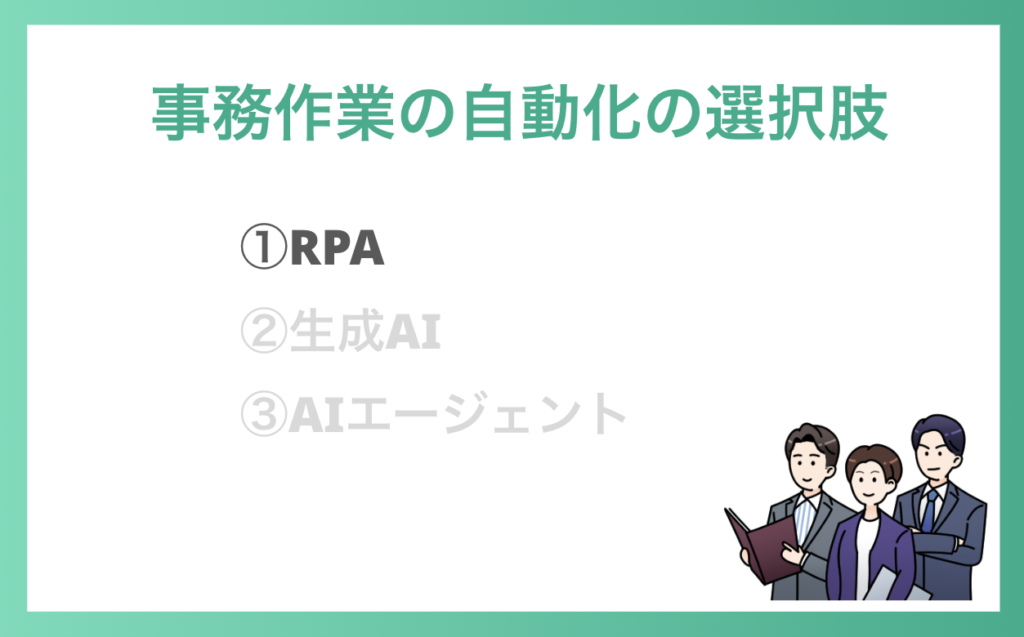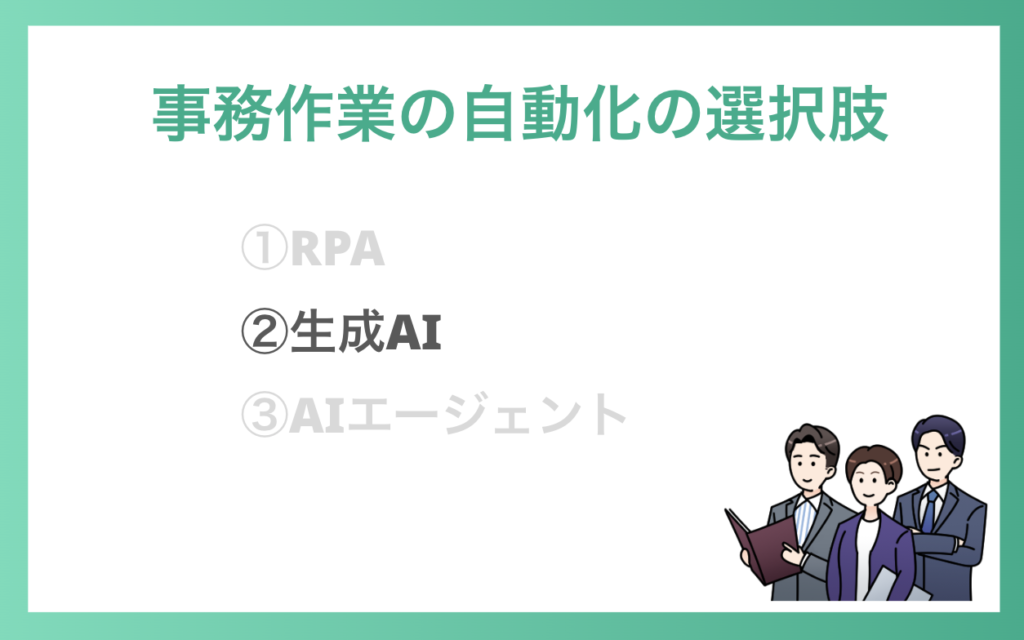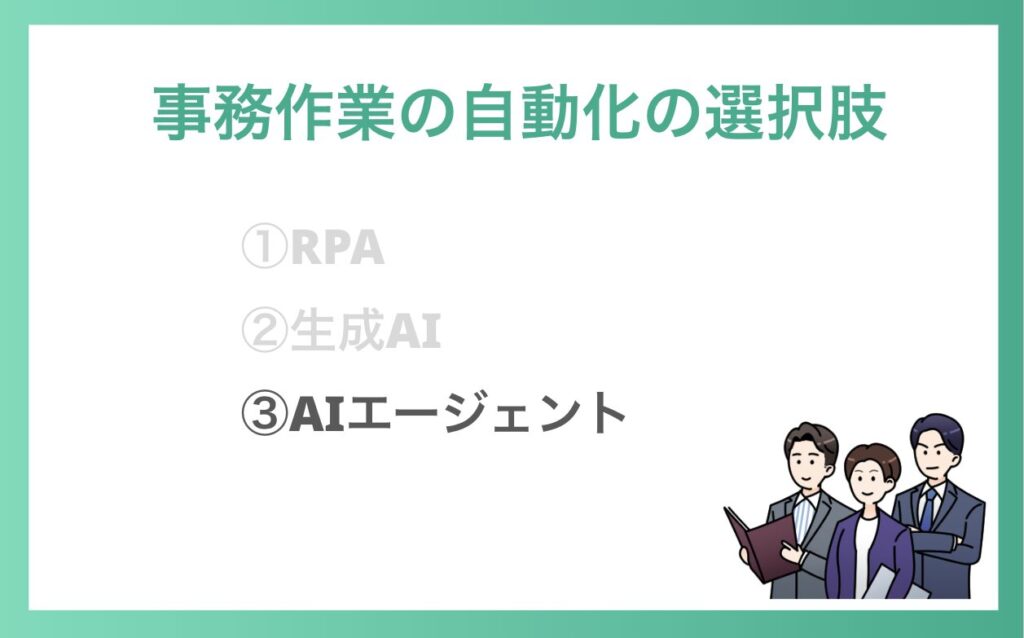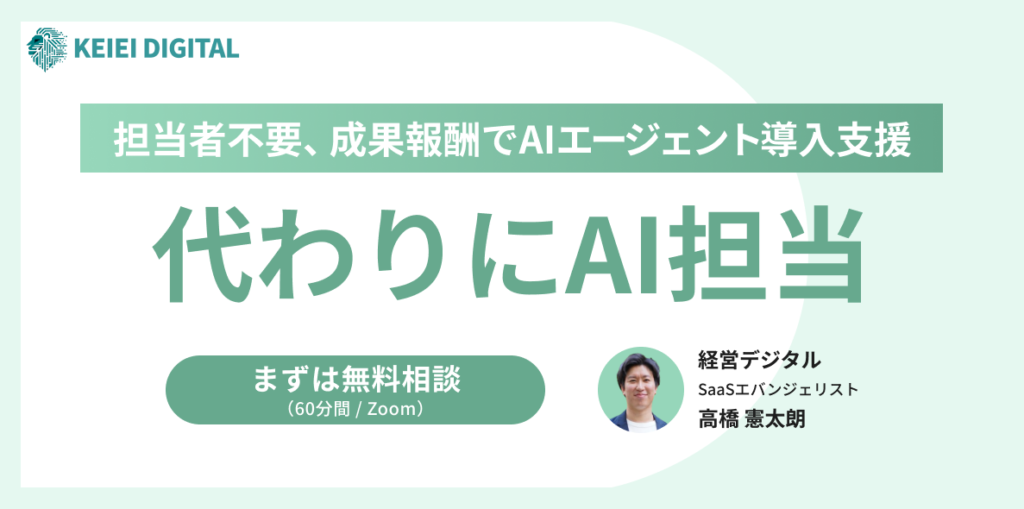これまで事務作業の自動化といえばRPA(ロボットによる定型作業の自動化)が主流でしたが、最近では生成AIやAIエージェントといった新しい技術が急速に進化。
選択肢が増える一方で、「自社にはどれが合うのか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、2025年時点で注目される“事務自動化の三大手段” ― RPA・生成AI・AIエージェント ― を徹底比較。
それぞれの強み・向いている業務・選ぶべきタイミングを整理し、「目的から逆算して技術を選ぶ」ための判断軸をお届けします。
ツール選びに悩んでいる方こそ、ぜひご一読ください。
はじめにおさらい|「RPA」「生成AI」「AIエージェント」とは?
事務作業の自動化を検討する際、まず押さえておきたいのが各技術の特徴と向き不向きです。ここでは、主要な3つの手段について基本的な特徴を整理しておきましょう。
| 項目 | RPA | 生成AI | AIエージェント |
|---|---|---|---|
| 役割 | 人の定型操作を再現する | テキスト生成や要約などを行う | 人の判断・対応を代行する |
| 主な対象業務 | データ転記、ボタン操作、帳票出力など | メール文作成、議事録要約、FAQ対応など | 予約対応、日程調整、Slackでの社内応対など |
| 操作形式 | ルールを登録して自動操作 | プロンプト入力(例:ChatGPT) | 外部連携込みで自律的に稼働 |
| 向き不向き | 単純・繰り返し作業に強いが柔軟性に欠ける | 柔軟性があるがビジネスロジックは不得意 | 柔軟+実務的。設計次第で高い自動化が可能 |
まずは、各技術の特徴について整理しました。

-
-
【2025年最新】AIエージェントと生成AIの違いとは?仕組み・活用シーンを徹底解説
続きを見る
それぞれの特徴がわかったところで、ここからは具体的に「どんな業務に向いているのか?」を見ていきましょう。
1. RPA|「ルールが明確な作業」はこれ一択
最初に紹介するのは、自動化の“王道”ともいえるRPA。ルール通りに動かす作業には、今も変わらず強い味方です。
強み
- Excel入力→システム転記など、ルール化された事務処理に最適
- プログラミング不要で導入しやすい(例:UiPath)
弱み
- イレギュラー対応が苦手、画面構成の変更に弱い
- ツール費・保守コストがかかる
向いているケース
- 経理の定型伝票入力
- ECの受注データ取り込み
- 毎月のレポート出力や転記
RPAは、特に“動きが決まっている”業務において、もっとも導入効果が高い選択肢です。
2. 生成AI|「考える・書く」業務を一気に効率化
次に紹介するのは、ここ数年で一気に存在感を増した生成AI。ChatGPTなどの登場で、言語系業務が驚くほど効率化されています。
強み
- 文書の生成、要約、改善など「言語処理」が得意
- ChatGPTやClaudeなど、すぐ試せるサービスが豊富
弱み
- 回答にムラがある(幻覚)
- セキュリティ配慮が必要(業務利用には注意)
向いているケース
- 営業メール・お礼メールの作成
- 会議録の要約、報告書のたたき台作成
- FAQのドラフト生成
「人が書く・考える」作業に負担を感じているなら、まずは生成AIを試してみる価値があります。
3. AIエージェント|「人の判断を代行」できる次世代型
そして今、最も注目されているのがAIエージェント。単なるツールではなく、業務フローそのものを動かせる存在です。
強み
- 外部システムと連携して自律的に行動
- 柔軟な対応と業務フロー全体の効率化を両立
弱み
- 設計や初期構築に知識やコストが必要
- 運用中の改善・学習にコストが必要
向いているケース
- 予約フォームの入力案内や日程調整
- Slackでの自動応答・社内エスカレーション
- 問い合わせの初期対応やスクリーニング
業務全体の再構築や効率化を目指すなら、AIエージェントは非常に強力な選択肢となります。

-
-
【2025年版】AIエージェントとは?仕組みと活用事例を徹底解説
続きを見る
4. 比較まとめ|結局、どれが自社に合うの?
ここまでの内容をもとに、自社の状況に合わせた選び方を整理しましょう。
| ケース | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 手順が固定された事務作業 | RPA | 操作の再現が得意で、コスパ◎ |
| テキストベースの業務改善 | 生成AI | 柔軟に“考えてくれる”ので汎用性◎ |
| 一連の業務を自動で任せたい | AIエージェント | 他ツールとの連携で業務そのものを代行可能 |
5. 導入時のポイント|“目的から逆算”して選ぶ
どの技術を使うべきか悩んだら、「自社が何を自動化したいのか?」から逆算して考えることが重要です。
判断に使える3つの視点
- 作業の種類:単純作業か?創造的業務か?判断を伴うか?
- 作業の範囲:一部工程だけか?業務全体か?
- 柔軟性の必要度:どれくらいイレギュラーに対応する必要があるか?
この3軸を基にすれば、「なんとなく便利そう」でツールを選ぶリスクを防げます。
判断パターン①|とにかく転記や操作が多い会社
- Excelからシステムへの転記
- 帳票出力や定期的なチェック作業
- 入力内容がルール化されている
この場合はRPAが最適。最小コストで効果が出やすく、初期導入にも向いています。
判断パターン②|問い合わせ対応や日程調整が多い会社
- お客様とのやり取りが多い
- 日程調整や案内が頻繁に発生
- Slackや予約フォームなどツールも混在
この場合はAIエージェントが有効。システム連携も含めて人の判断業務を代替できます。

-
-
【2025年最新】おすすめAIエージェントツール8選を徹底比較|サービス特徴や活用シーンも解説
続きを見る
まとめ|技術に振り回されず「目的起点」で選ぼう
事務作業の自動化には、RPA・生成AI・AIエージェントという強力な選択肢が揃っています。
大切なのは、どの技術が一番新しいかではなく、
「自社の業務において、どの場面で・何を任せたいか」を明確にすることです。
- ルールが決まった作業:まずはRPAで着実に省力化
- 文章作成や考える作業:生成AIを取り入れて業務スピードを加速
- 判断や対応が必要な業務:AIエージェントで一歩先の自動化へ
技術を使うことが目的ではなく、
「人がやらなくてもよいことを、どこまで手放せるか」こそが自動化の本質です。
まずは小さく始めて、段階的に“深い自動化”へと進めていきましょう。

AIエージェント導入支援サービス:代わりにAI担当
代わりにAI担当の導入支援の特徴
- 担当者不要。社内のAIエージェント推進担当を丸ごとお任せ可能
- 導入前の社内の状況の整理から、実際の導入、導入後の改善まで一気通貫で支援
- 費用は成果報酬型。成果に応じた安心の明瞭会計。